はじめに~ポートフォリオの重要性
エンジニア転職を目指す人にとって、ポートフォリオは合否を左右する重要な材料です。
特に未経験や第二新卒の場合、履歴書だけでは実力を伝えきれません。企業は「この人は本当にコードを書けるのか?」「学んだことを形にできるのか?」をポートフォリオで判断します。
ポートフォリオは単なる作品集ではなく、技術力・課題解決力・学習姿勢を示す証明書です。完成度の高いものを準備すれば、それだけで採用担当者に強い印象を残せます。
しかし一方で、多くの人が「どんな作品を作れば評価されるのか」「GitHubに置くだけでいいのか」と悩み、間違った作り方で評価を下げてしまうケースもあります。
そこで本記事では、
- 企業がポートフォリオに求めるポイント
- 未経験でもできるポートフォリオの作り方
- やってはいけないNG例
- 転職活動での効果的な活用法
をわかりやすく解説します。
最後まで読めば、「企業に評価されるポートフォリオ」を自信を持って準備できるようになるでしょう。
企業がポートフォリオに求めるポイント
エンジニア転職において、ポートフォリオは企業が「応募者の素の実力」を判断するための重要な資料です。履歴書や職務経歴書では分からない部分を見られるため、企業が注目するポイントを理解して作成する必要があります。
ここでは、採用担当者が特に意識している4つの観点を紹介します。
① 技術力の証明
ポートフォリオの最初のチェックポイントは「きちんとプログラムを書けるか」です。
- コードが整理されているか(無駄な記述やコピペばかりになっていないか)
- 使用している言語やフレームワークの理解が感じられるか
- アプリとして成立しているか(CRUD機能、ログイン機能などが動くか)
例えば、未経験でも「ブログ投稿アプリ」「ToDo管理アプリ」のように基本的な機能を実装できていれば、基礎力があると判断されやすくなります。
② 論理性と工夫
採用担当者は単なる完成品だけでなく、「なぜその技術を使ったのか」「どのように実装を工夫したのか」に注目します。
READMEや面接で、以下のような説明ができると強みになります。
- 選択理由:「なぜLaravelを選んだのか?」「なぜデータベース設計をこのようにしたのか?」
- 工夫の内容:「処理速度を上げるためにキャッシュを使った」「UIを改善してユーザーが直感的に使えるようにした」
つまり、考えながら作ったことを伝える力が評価されるのです。
③ 継続力・学習意欲
「完成品を一度作って終わり」ではなく、「改善を続けているか」も大きな評価ポイントです。
GitHubのコミット履歴を見れば、
- 定期的に更新しているか
- バグ修正や機能追加に取り組んでいるか
- 新しい技術を試しているか
が一目で分かります。企業は短期間で作ったものより、コツコツ育てているプロジェクトから学習意欲を感じます。
④ わかりやすさ(第三者目線の配慮)
採用担当者はエンジニアだけではありません。人事担当者や現場以外の人が見ることもあります。
だからこそ「誰が見てもわかりやすい」工夫が重要です。
- READMEに開発環境・使用技術・機能一覧・使い方を明記
- 実際に動くデモサイトやスクリーンショットを用意
- 導入手順を簡単にまとめる
これがあるだけで「応募者の気配り」や「伝える力」が伝わり、評価が大きく変わります。
まとめると、企業は 「動くアプリがあるか」ではなく「この人が成長できるか」 を見ています。
技術力だけでなく、論理性・継続力・伝える力まで意識して準備することで、未経験でも強い印象を残すことができます。
未経験でもできるポートフォリオの作り方
ポートフォリオは、いきなり完璧なものを作る必要はありません。大切なのは 基礎を押さえた上で、少しずつ工夫を加えていくこと です。ここでは、初心者でも取り組みやすい手順を紹介します。
① テーマを決める
まずはシンプルな題材から始めましょう。企業が注目するのは「派手さ」ではなく「基礎力」です。
おすすめ題材
- ToDoリストアプリ(CRUD機能を確認しやすい)
- ブログ投稿アプリ(ユーザー管理・記事投稿・編集・削除)
- 勤怠管理システム(現場業務に近く、実務をイメージしやすい)
- 書籍レビューサイト(外部APIとの連携を見せられる)
ポイントは「日常生活や業務に役立つシンプルなアプリ」を選ぶことです。
② 設計を行う
ただ作るのではなく、設計を形に残すこと が評価につながります。
- ER図(テーブルとリレーションを図示)
- ワイヤーフレーム(画面の簡単なレイアウト図)
これをREADMEやスライドに入れておくと「考えて設計できる人」だと伝わります。
③ 実装とコード整理
次に実装ですが、ここでは「見た目」よりも「基礎的な処理」が大事です。
- 命名規則を統一する(例:キャメルケース / スネークケース)
- 適度にコメントを残す(意図が分かるコードは好印象)
- コードをフォルダごとに整理する(MVCの考え方を意識)
「動けばいい」ではなく「他人が読んでも理解できる」コードを意識しましょう。
④ 公開とデプロイ
アプリは 「動く状態」で公開すること が大切です。コードだけでは採用担当者が確認できないため、必ずデプロイしましょう。
公開方法の例
- GitHub Pages(静的サイト向け)
- Heroku(初心者向け)
- Vercel / Netlify(フロントエンド向け)
- AWS(本格的なインフラ学習も兼ねられる)
リンク切れはマイナス評価になるので、公開後も動作確認を忘れずに。
⑤ READMEで工夫点を説明する
READMEは「あなたの代わりに面接官へ説明してくれる資料」です。
書いておくべき内容
- 使用技術(言語・フレームワーク・DB)
- 実装した機能一覧
- 工夫したポイント(例:ログイン機能のセキュリティ対策)
- 今後改善したい点
READMEが整理されているだけで「伝える力がある人材」として印象が上がります。
⑥ 初心者におすすめの題材例まとめ
- ToDoリストアプリ(基礎力アピール)
- ブログ投稿アプリ(CRUD+認証機能)
- 書籍レビューサイト(API連携の経験を見せられる)
- 簡易ECサイト(商品管理+カート機能)
まずはシンプルに作り、慣れてきたら「機能追加」で差をつけるのがコツです。
ポートフォリオは 「作る → 見せる → 説明する」 の流れを意識することが大切です。
ただ動くだけのアプリではなく、「考えながら作った痕跡」 を見せることで、企業の評価はぐっと高まります。
やってはいけないNG例
どれだけ努力してポートフォリオを作っても、作り方を間違えると 「評価が下がる」
可能性があります。ここでは、未経験者がやってしまいがちなNG例を具体的に紹介します。
① チュートリアルをコピペしただけ
ProgateやUdemy、YouTubeのチュートリアルをそのまま写したアプリは、
採用担当者にすぐ見抜かれます。
- コードが独自性に欠ける
- 工夫や改善が見られない
必ずオリジナル要素(機能追加やデザインの改善)を加えましょう。
② READMEが空白、またはリンク切れ
せっかくアプリを公開しても、READMEが空白だと
「何を見ればいいのか分からない」と判断されます。
さらにデプロイ先のリンクが切れていると「管理が雑」「責任感がない」
という印象につながります。
READMEは必須、リンク確認は面接前に必ずチェックしましょう。
③ コードが整理されていない
- 変数名や関数名がバラバラ
- 不要なコードが大量に残っている
- コメントが一切ない
これでは「共同開発に向かない」と判断されます。チームで読みやすいコードを意識しましょう。
④ セキュリティを無視した実装
採用担当者は意外とセキュリティ面もチェックしています。
- パスワードを平文で保存している
- 入力チェックがないフォーム
- SQLインジェクションに無防備
完璧でなくても構いませんが、最低限のセキュリティ対策(ハッシュ化、バリデーション)は実装しておきたいところです。
⑤ デザインが極端に崩れている
見た目は二の次とはいえ、レイアウトが大きく崩れていると
「使いづらい」と感じられてしまいます。
- ボタンが隠れている
- スマホで表示すると文字が読めない
シンプルでも良いので、基本的なUI/UXは意識しましょう。
NG例に共通するのは 「採用担当者の立場を考えていない」 ことです。
ポートフォリオは「自分が満足するもの」ではなく、
「相手に伝わるもの」 でなければ評価されません。
転職成功につなげる活用法
ポートフォリオは「作って終わり」ではありません。大切なのは、転職活動の中で
どう見せるか、どう語るか です。ここを工夫することで、採用担当者に強い印象を与えられます。
① 面接での説明方法
面接では「何を作ったか」だけでなく「どう作ったか」「どんな課題があったか」を語れると
評価が高まります。
- 工夫した点:「UIを改善して直感的に操作できるようにした」
- 苦労した点:「認証機能の実装に時間がかかったが、公式ドキュメントを読み込み解決した」
- 改善点:「現状は機能が限定的だが、今後はテストコードを追加したい」
完璧さよりも、試行錯誤して成長する姿勢を伝えることが大切です。
② 学習ログや技術記事とセットで見せる
ポートフォリオ単体ではなく、学習の過程を見せると説得力が増します。
- GitHubのコミット履歴 → 継続的な努力をアピール
- QiitaやZennの記事 → 学んだことをアウトプットできる力を示す
- Twitterやブログ → 学習を習慣化している姿勢を見せられる
「アウトプットできる人」は、現場でも成長が早いと評価されます。
③ 未経験でも評価される工夫
- READMEで「技術選定の理由」を説明する
- デプロイ済みのアプリを用意し、採用担当者がすぐ試せるようにする
- 小さなアプリを複数作ることで「幅のある学習」をアピール
実務経験がなくても、「自走力」や「学ぶ姿勢」 を示せば評価されます。
④ フリーランス・キャリアアップへの応用
ポートフォリオは転職だけでなく、その後のキャリアにも役立ちます。
- フリーランス案件では、過去のポートフォリオが「実績」として活用可能
- キャリアアップ転職では、最新の技術を取り入れた改訂版ポートフォリオ が武器になる
一度作ったら終わりではなく、常に更新していく資産と考えると良いでしょう。
まとめると、ポートフォリオを「作品」ではなく「自己PRツール」として活用することが、
転職成功のカギです。
「作る力」+「伝える力」+「継続する力」 をセットで見せることで、
未経験でも企業に強くアピールできます。
まとめ
エンジニア転職において、ポートフォリオは単なる作品ではなく 「成長の証明」 です。
企業は「どんなアプリを作ったか」以上に、そこから見える 技術力・論理性・学習意欲・伝える力 を重視しています。
本記事で解説したように、評価されるポートフォリオには以下のポイントがあります。
- 基礎力を示せるシンプルな題材を選ぶ
- 設計・README・デプロイまで整えて「伝わる形」にする
- オリジナリティや工夫を盛り込み、思考のプロセスを示す
- **NG例(コピペ・リンク切れ・コードの乱れ)**を避ける
- 面接や学習ログと組み合わせて 「継続力」や「成長姿勢」 を伝える
ポートフォリオは一度作って終わりではなく、更新し続けることでキャリアの資産になります。
小さな改善や新しい技術の導入を積み重ねていくことで、「この人なら伸びる」と企業に思わせることができるでしょう。
転職を成功させたい方は、まず一歩踏み出して 最初のポートフォリオを形にすること から始めてみてください。
その努力の積み重ねこそが、あなたのキャリアを大きく広げる力になります。

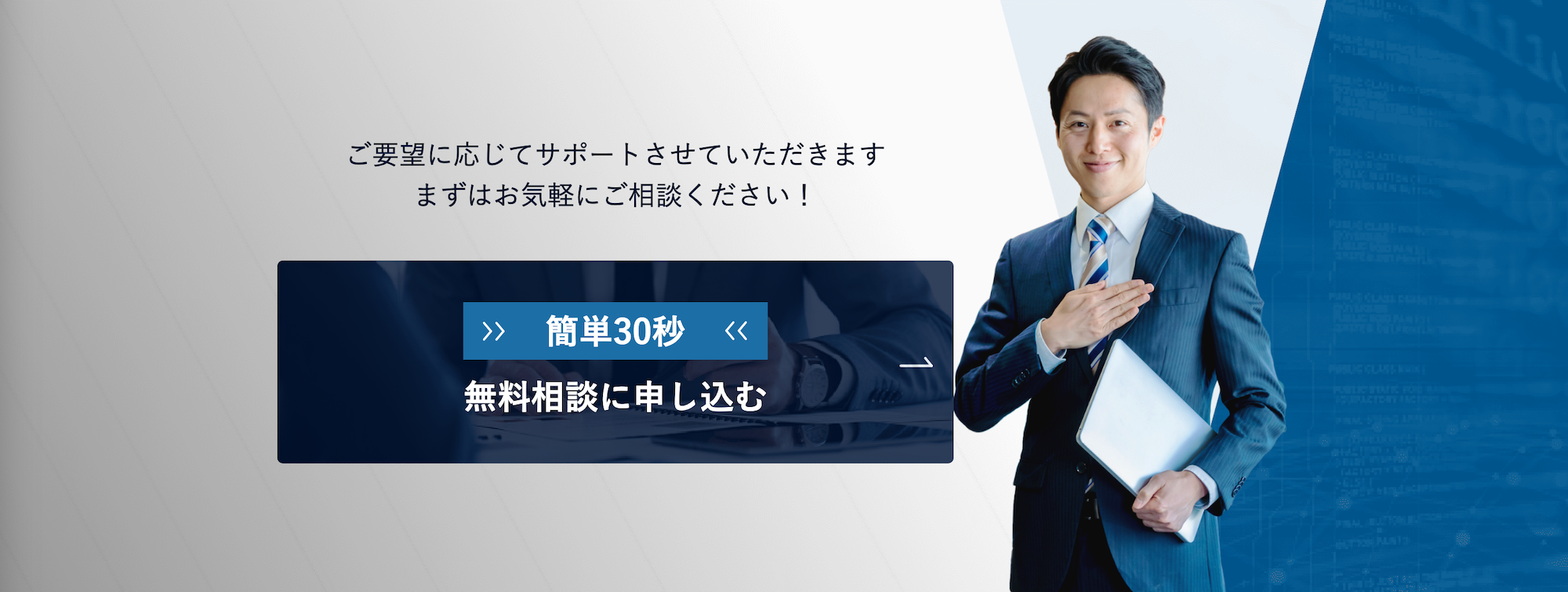
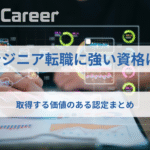






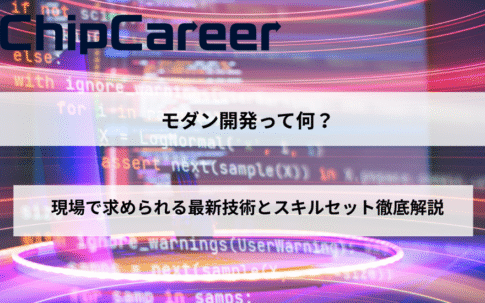
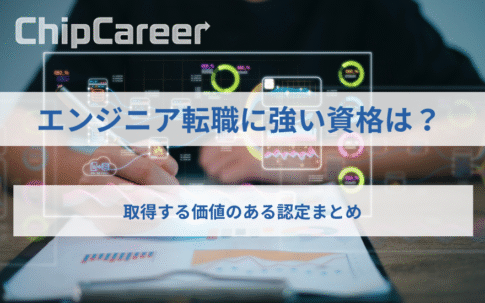





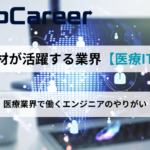
コメントを残す